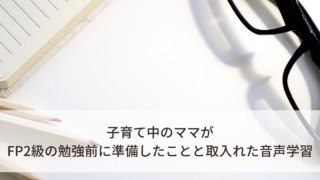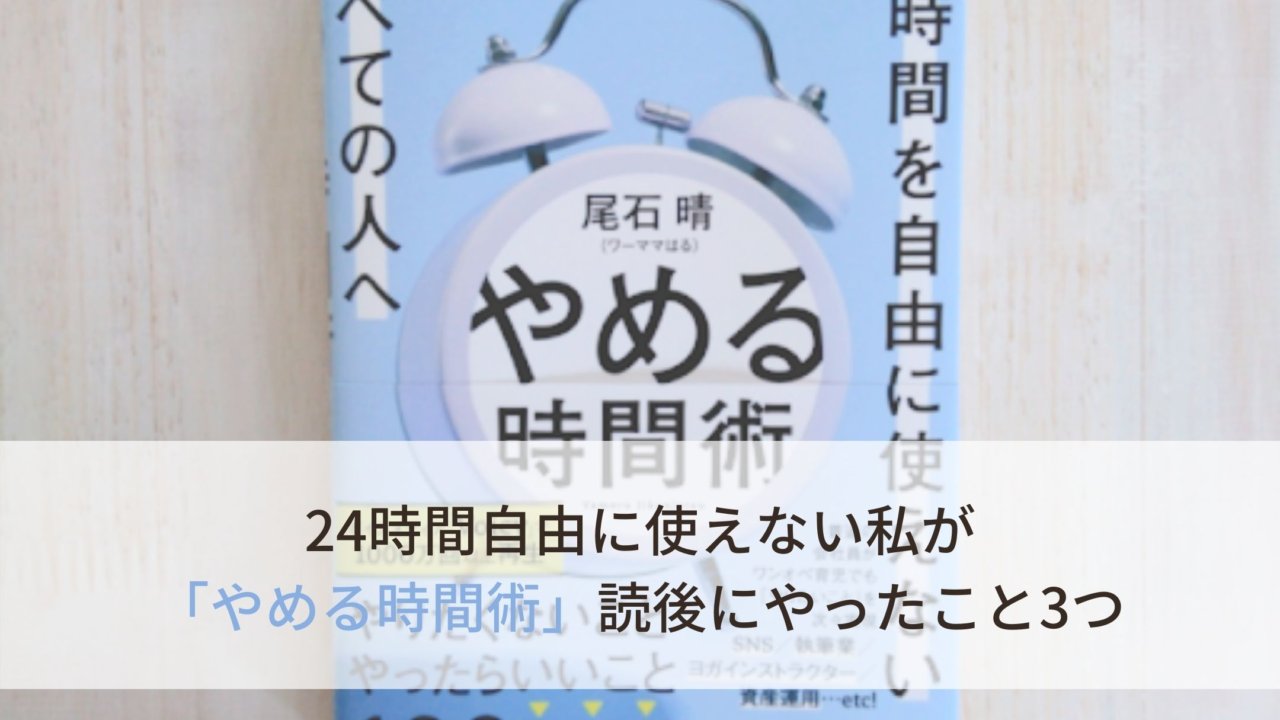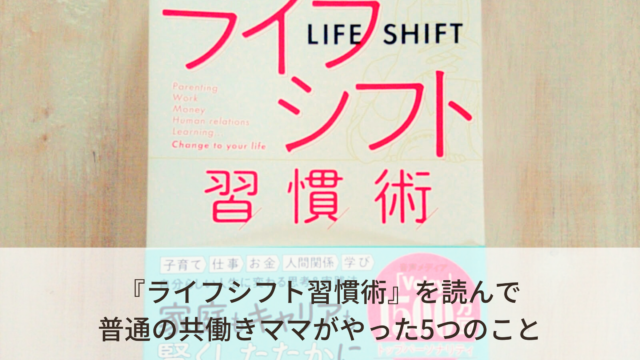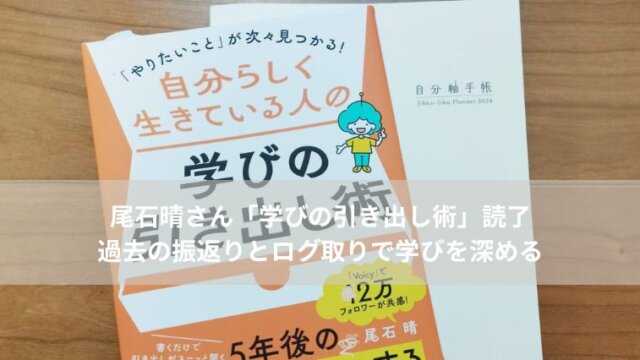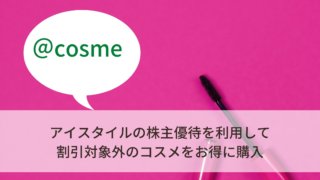こんにちは、株歴8年目の兼業投資家ママブロガーのつんつん(@ZPuriko)です。
育休中にワーママはるさんの音声配信Voicyと出会って、あれやこれや考えることが好きになったり、ヨガ始めたり、はるさんからよりよく生きるヒントをいただいています。
時間の制約があり24時間を自由に使えない人の中の一人である私が「やめる時間術」を読んで得たヒントをもとに実践したこと3つをここに残しておこうと思います。
この記事は、こんなことについて書いています。
時間に制約があり24時間自由に使えない私が、「やめる時間術」を読んで実践したこと
改めて自己紹介しますと、私自身は育休から復職して半年の共働きワーキングマザー(フルタイム勤務)、5歳年中・2歳半の二児を育てていて、24時間を自由に使えない人の一人です。
ちょうど働きすぎて家庭も仕事も破綻してていてどうやって立て直そうか考えているときに、「やめる時間術」を手に取りることができて、ほんまラッキーな私。
私のようなワーママだけでなく、介護・子育て等で自分の時間に制約がありながら生活をしている全ての方におすすめできる本です!

「やめる時間術」から学ぶ引き算の大切さ
引き算はできているか?を自分に問う
価値観を見直す時間の引き算
「時間の引き算」とは、自分の人生の優先度に基づいて、優先度の低いものにかける時間をやめること
やめる時間術 p.89より引用
ワーママはるラジオで教えてもらったことや心構えをもって、半年前に復職をしたはずなんですが、
いざ子育て家事などやりながら働いてみると、バランスを崩してしまっていた私。
こうなったのはなんでかな?
フルタイムで働くだけでもいっぱいいっぱいなのに、さらに欲張ってしまって、会社の人からの評価まで得ようとしてたからですね。
そう、答えは簡単で、引き算ができていなかったんです。
「あれもこれも欲張るな!」引き算の大切さ
去年の2月に開催されたワーママはるさんのセミナーに参加した時も感銘を受けたんですが、はるさんは引き算の大切さを教えてくれるんです。
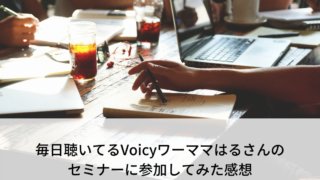
「やめる時間術」は、時間の使い方から人生を見直す本。
私が一番惹きつけられるのは、引き算の実践方法。これを学ぶことができます。
ついつい引き算をせずに足し算をしてしまうタイプなのですが、
「あれもこれも欲張るな!」「人生はトレードオフ!」とはるさんの優しい声が自然と聞こえてくるようになりました(こわい?)
引き算は自分の価値観を変えるほどの大仕事である!
「やめる時間術」をヒントに実践したこと3つ
やめる時間術がぎっしり詰まった本なのですが、私が読後に主に実践したことを3つご紹介します!
- 第3章 やめる時間術のカギ
時間の「引き算」 - 第4章 時間の引き算応用編
- 第2章 タイムパフォーマンス向上術
大事な仕事はゴールデンタイムにする
①子供と一緒に帰宅から就寝までの時間を見直した
子育ての思い込みロック
引けないと思っている時間の中に思い込みは含まれていないか?
「やめる時間術」よりp.124 より引用
今使っている手帳(自分軸手帳)で24時間は棚卸済み。
「やめる時間術」を読んだ後に、もう一度24時間の棚卸済みのスケジュールをよくよく見ました。
子供の機嫌や体調によってずれるのであまりきちきち時間を意識しすぎると私も子供も疲れてしまうかな?という考えであえてゆるくしておいた、保育園から帰宅後から就寝までの時間。
この時間を子供(年中)と一緒に見直すことにしました。
はるさんが言っているように保育園でやってるが家でできないわけないし、時間を意識して過ごすことで時間の概念を子供に学んでもらうのがいいな、と。
敢えて時間を気にしすぎないように過ごしてきた保育園から就寝までの時間。
ちょっと考えを改め、娘👧と一緒に、
現状と
理想
を描いてみた。娘👧の理想は、帰宅してから寝るまでずっとパパ🤓と一緒がいいみたい😁 pic.twitter.com/Wy0QjtdzD4
— つんつん@兼業投資家ママブロガー (@ZPuriko) January 18, 2021
娘と一緒に理想と現実を話しながら、絵を交えて理想と現実を書きました。
現状を書き出した後に「9時には寝たいね」、
「9時に寝るにはお風呂は?ご飯は?歯磨きは?明日の保育園の準備は?いつすればいいんだろうね?」と、パズルを埋めていく感覚でやることを埋めていきました。
実施時間を決めたあとに、「だれがどうやってやる?」を娘と決めました。
親が一方的に決めたものではない娘本人も一緒に考えて書いた寝るまでの時間割なので、寝る前までにには何をやるというのは今まで以上に意識できているような雰囲気があります。
一人でできないと思ったら子供と一緒にやる!(子供を巻き込む)
②メニューを固定化!献立に悩む時間の削減
やりたくないリストを作る
メニューの固定化は思考や行動も引き算できるのでものすごく有効です。
「やめる時間術」 p.109ページより引用
私はすごく献立を立てるのが嫌いなんですが、様々なものを食べさせなければならないという使命感で「いろんなメニューを作らなければならない」に疲弊していました。
だけど色々なメニューを作ってみたところで上の子と下の子の好みが違いすぎて、せっかく作ったもメニューが食べてもらえず残ってしまうということが多々あり、地味にストレスでした。
やめる時間術の引用個所を読んで、
元々金曜日はカレーの日と決めてたんですが、家族全員が好物の豚汁を水曜日に設定したことによって、水・金だけメニューを考えればよくなり、子供達が食べないという心配もなくなりました。
子供二人が食べるメニューの種類にこだわるよりも、確実に食べてもらえるメニューを提供することに決めたことで、献立作りに悩む時間の削減と気持ちよく夕食を終えることができるようになりました。
娘👧と息子👦の食べ物の好みが違いすぎる問題で試行錯誤した結果、
二人ともが好んで食べてくれる豚汁の採用率をあげてみることにした!「毎週水曜日の夕食は豚汁にすることにした」と夫に話したら、
なんと、夫が豚汁作ってくれてた。
なんと、素晴らしい✨
(毎週作ってくれたらいいな)— つんつん@兼業投資家ママブロガー (@ZPuriko) January 20, 2021
メニューを固定化したことによって夫が豚汁を作ってくれるというミラクルも起こりましたた!
まさかのメニュー固定化で、食べ手も人作り手もみんなが楽しい食卓になる
➂職場のメンバーのタイムパフォーマンスを向上させる
意志力と思考力を考慮したスケジューリングをしよう
「やめる時間術」 p.86より引用
こんなご時世なのに深夜まで残業している私の上司。
彼の残業の原因は介護や育児で時間の制約があるメンバー(私含む)の存在のせい、在宅勤務が増えたせいと決めつけられてました。
時間の制約があるメンバー(私含む)はたまったもんじゃないし、めちゃくちゃ働きにくいので、上司含むメンバーへ働き方改革を提案しました。
チームのみんなに一日どんなスケジュールで仕事してるか聞いてみたら、チームメンバー全員が思いついた順で適当にやっている上に、スケジュールを見える化していないという現状。
上司はメンバーの業務をほぼ管理できていない・・・上司って一体なんの仕事してんの?(不安)
場当たり的に仕事をしているチームメンバーに対して、やめる時間術を参考に、
まずはスケジューラに一日の作業内容を入力して見える化を徹底し、タイムパフォーマンスをあげる訓練を始めてもらっています。
上司の残業の原因が時間制約のあるメンバーや在宅勤務のせいになっている(という、ほんまかいな?な)現状を変えたくて始めた取り組みですが、職場の生産性向上するということは、私の仕事の時間を短くできるにつながるので、とってもやりがいをもってやってます。
やめる時間術は職場でも使える!
全ての人に読んでほしい「やめる時間術」
「やめる時間術」読んでみて、介護・子育て等で自分の時間に制約がありながら生活をしている全ての方に是非とも読んでいただきたいなと思う内容の本でした!
私が「やめる時間術」の読後に実践したことは、
3章、2章、4章を参考に、
- 子供と一緒に帰宅から就寝までの時間割を考える
- 家庭で夕食のメニューを一部固定化する
- 職場で業務の見える化・タイムパフォーマンスの概念を浸透させる
です。
はるさんから教わった「時間の価値」。
これからもたくさん試行錯誤すると思うけど、私は、私が決めていく人生を歩みます。
令和3年 2月
自宅の仕組化・効率化も始めました。

FP2級を受けるために引き算をしました。